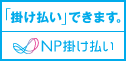2011年7月4日
ミズキ科ミズキ属の落葉樹で、20m程の高さに成長します。

鹿の角状に分かれた枝ぶりが特徴。
同じミズキ科の仲間としては、クマノミズキや庭木として人気のあるハナミズキ、ヤマボウシ、サンゴミズキ、サンシュウなどがあります。
ミズキの名前の由来は、樹皮を傷つけたり、枝を折ったりすると多量の水が滴り落ちるという特性からきています。
ミズキの木は、冬を過ぎて日が延びるにつれ、樹皮の吸い上げはなはだしくなるため、こういう現象がおきます。
こうした現象は、カエデ類などにも共通してみられるが(メープルシロップ)、カエデ類には樹皮中に相当の糖分が含まれているのに対して、ミズキでは糖分の含有はきわめて少ない。
花は白色の小花だが、扇状に咲くと一面が白くなるほどです。秋には赤い果実が熟して、野鳥やヒヨドリが集まり、種子を遠くまで運んでくれる。英名の「dogwood(ドッグウッド)」は、この樹皮を煎じた煮汁を使って犬を洗うと皮膚病が治るという話にちなんでいるみたいです。
日本では、材面が白く美しいことから、ろくろ細工や寄木細工、象眼や椀物、白箸などにも利用されています。

また、材の白さから、アイヌ民族ではこの木で特別に神に敬意を表するときの語弊(神への捧げもの)を作った。これは天国では銀に相当するもののようです。
ミズキの材そのものは肌目が精で、木理は通っています。やや硬め。あまり大きな材が取れないことと耐朽性が高くないことから建築用材としては不
向きとされているが、心材と辺材の色の差がほとんどなく、しっかり乾燥させてから使えば家具材としては有用です。
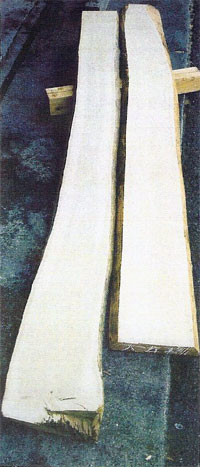
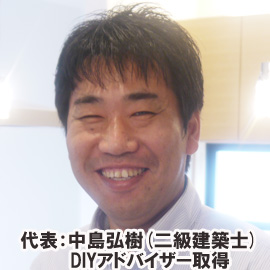
マルトクショップは、木材(無垢材・集成材・積層材)のフリーカット販売・床材(フローリング材)の通販専門店です。
無垢材・集成材をお好みの寸法にカット、木材のサンプルを送料無料でお届け、施主支給など、お客様のニーズにあわせたプランをご用意しています。
定休日は、お電話での対応はお休みさせていただいております。サイトからのご注文・メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますが、ご連絡は翌営業日になりますのであらかじめご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
コンテンツ
© 2025 MARUTOKU LUMBER Co., Ltd. All Rights Reserved.