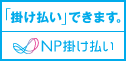2012年3月30日
前回のブログで、日本の「能」で使用されている能面にはヒノキが使用されていることをお話ししました。
「能」の世界におけるヒノキの使用は、お面だけではありません。
「能」の舞台は、能舞台(のうぶたい)といって、ここにもヒノキが使われています。
本物の能舞台は、木曽で産出される尾州檜(びしゅうひのき)の柾目の長材だけで作られます。
尾州檜とは、木曾谷に生育する樹齢300年以上の天然の檜の名称で、非常に貴重な木材と言えるでしょう。

江戸時代、ヒノキを使用しての舞台制作が許されていたのは、「能楽」「歌舞伎」などの
幕府に認められた劇場だけでしたが、現在では、国立劇場や歌舞伎座という格式の高い劇場の舞台も
尾州檜で造られています。
格式の高い劇場の舞台にしか使われないヒノキ。
転じて、「檜舞台」という表現は、自分の手腕を人々に見せる晴れの場所という意味で使われています。
天然ヒノキ自体は、福島県以南の本州と四国および九州と広範に分布していますが、群生地となると、
木曽谷以外にはほとんどありません。多くのヒノキは植林によって人工的に育てられたものです。
水湿腐蝕に強く非常に耐久性に優れているため、風呂用具から仏像彫刻と幅広く使用されているヒノキは、
「良い木材」の代名詞とも言えます。
神社やお寺の柱などにも使われている一方で、ヒノキは別名「火の木」とも呼ばれ、
家の柱にはヒノキを使わずに、大壁柱には杉を、床柱には槐(えんじゅ)を使うと、
火除けとなって家に火を呼ばないとの言い伝えがあったりもしますから面白いですね。
関連記事
« 木の雑学「能面」 木の雑学「体育館の床」 »
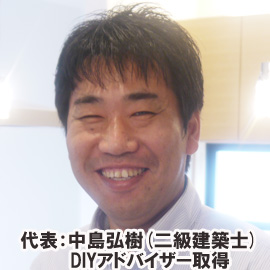
マルトクショップは、木材(無垢材・集成材・積層材)のフリーカット販売・床材(フローリング材)の通販専門店です。
無垢材・集成材をお好みの寸法にカット、木材のサンプルを送料無料でお届け、施主支給など、お客様のニーズにあわせたプランをご用意しています。
定休日は、お電話での対応はお休みさせていただいております。サイトからのご注文・メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますが、ご連絡は翌営業日になりますのであらかじめご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
コンテンツ
© 2025 MARUTOKU LUMBER Co., Ltd. All Rights Reserved.